こんにちは。過去に就労移行支援事業所で4年間勤務し、100人以上の就職支援・1000件以上の求人票を見てきたキャリアコンサルタントの笠見です。今回は、面接で「特性と配慮事項」を聞かれたとき、企業が特に重視していることや、面接での具体的な伝え方をご紹介します。
今回は、以下の3点について書いています。
- 配慮事項の作り方5ステップ
- 配慮事項を伝えるコツ
- 面接での事例紹介
今回ご紹介する配慮事項の作り方5ステップに沿って準備をすることで、配慮事項を書くことができます。また、配慮事項をうまく伝えるためのコツをご紹介しています。
最後に、実際の面接での流れを事例紹介します。
◆ なぜ “配慮事項” は必ず聞かれるのか?
以外の4項目は今まで私が同行した採用面接で、聞かなかった企業はほぼありません。
- 障害名
- 手帳の種別、等級
- 障害特性
- 配慮事項
そして、この4つの項目の中でも、今回ご説明する配慮事項を丁寧に聞く企業は多いです。なぜ配慮事項を聞くのか、その理由を説明します。
配慮事項をなぜ聞くのか?
面接で「配慮事項」が聞かれるのは、主にこの2つの理由からです。
一つ目は、企業にとって、求めている配慮が提供可能かを確認するため
例えば車椅子の方がエレベーターの無い企業に対し「エレベーターを各階に設置してもらいたい」と言っても、すぐに対応することは難しいですよね。周りの音が気になるので個室で仕事をさせてほしい、と言っても、個室のない会社であれば対応できません。
企業は配慮事項を聞きながら、「自分の企業では求められている配慮を対応できるかどうか」を確認しています。
二つ目は、応募者が自分の特性を理解し、“どう工夫しているか”を持っているかを見たいから
ただ「できない」ではなく、「どうやってできるようにするか」の視点が重要です。
自身の特性に対して、自己理解・自己受容できていない方は、自身の特性に対して「自分なりの対策」を持っておらず「できないからしょうがない」というようなあきらめのような態度が滲み出ています。
できないからしたくない、やらせないでほしい、ではただのわがままです。自分の苦手なことに対してどうしたらできるか、という視点で試行錯誤を繰り返していきましょう。
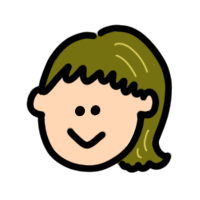
試行錯誤しても、どうしてもできないこと=配慮なんです。
ADHD、Aさんの事例
Aさんは同じ作業を繰り返すことが苦手で、単純なデータ入力はすぐに集中力が切れてしまいます。そこでAさんはデータ入力を30分単位で区切り、他の業務と入れ子にしてみることにしました。
すると、今まで集中できなかったデータ入力でも30分と決めたことで驚くほど集中でき、仕事がどんどんはかどったそうです。データ入力は集中力が続かない、というのはAさんの特性です。
その特性に対して試行錯誤した結果、仕事の成果を出すために、色々な業務と交互に行わせてもらいたい、という配慮事項を会社にお願いしました。
配慮事項の作り方:5ステップで整理する
| ステップ | やること |
|---|---|
| STEP 1 | 過去で「いつも困ること」を思い出してリストアップする(例:集中が切れやすい/複数の指示が混乱するなど) |
| STEP 2 | なぜ起きたか原因を深掘り:状況・環境・自分の思考などを具体的に書く |
| STEP 3 | 自分でできる改善策を考える(例:作業を区切る/チェックリストを作る/途中で休憩を入れるなど) |
| STEP 4 | 周りの人や会社にお願いしたいことを明確にする(例:指示は1人から/変更があれば早めに知らせてほしいなど) |
| STEP 5 | 上記をまとめて、一つの文章にする。「私はこう困るので、こうしてもらえると成果が出せます」といった形に。 |
STEP1 困りごとをリストアップする
過去の経験で困ったこと、具体的にはすぐに解決できたものではなく、「いつも困っていること」を書き出していきましょう。思い浮かべるだけでなく、実際に書き出すことが大切。スマホやPCでもいいですし、もちろん手書きでもOK。
例:納期に間に合わないと思って急いで入力したらミスを連発してしまった。焦るとミスが多くなる。
STEP2 なぜ起きたのか?原因は?
次に、STEP1で書き出した困りごとは、どうしてその困りが起きたのか、原因を考えてみましょう。どんな状況だったのか詳しく書き足していきます。
どうして起きたのか、起こった時の状況や環境、背景についてできる限り詳しく書いていきましょう。
例:納期に間に合わない可能性があった。終わると思っていたのに終わりそうもなく、見積もりが甘かった。
STEP3 自分で改善できそうな工夫は?
STEP1で書いた困りに対して、自分で改善できそうな工夫はありますか?また今取り組んでいることはありますか?思い浮かぶだけ全て書き出してみましょう。
例:焦らないように計画的に進めていく、セルフチェックを2回行う、焦りが出たら休憩を取り、気持ちを落ち着かせる
STEP4 周りにお願いしたいことは?
周りに協力してもらいたいことを書き出します。これが配慮事項になります。こうしてもらえたら困りごとが起こりにくくなると思うことを書いていきましょう。
例:ダブルチェックをお願いしたい、納期がある場合は余裕のあるスケジュールにしてほしい
STEP5 書き出したことをまとめる
最後に、ここまで書き出したことを、一つの文章にまとめれば完成です。
例:焦るとミスが多くなってしまう。セルフチェックを欠かさず行い、丁寧に入力するようにしているが、ダブルチェックや、余裕のある納期設定をしてもらえるとミスがなくなる。
成果を出すための配慮、という観点を大事にしてください。
次に、よくある配慮事項例をご紹介します。
面接で使える “配慮事項+特性+対処” のセット例
- 急な予定変更は苦手なので、変更がある場合は予め教えてほしい
- マルチタスクは苦手なのでシングルタスクにしてほしい
- 指示の際は口頭より文章などのマニュアルがあると理解しやすい
- 複数人からの指示だと混乱するので、指示は一人から出してほしい
- パフォーマンスを安定させるために、一時間に一回休憩が欲しい
人事が特性と配慮事項をどのような観点で見ているのか
では次に、採用担当者は配慮事項のどこを重要視しているのかを説明します。
- 配慮事項で見ていること
-
- 障害を自己理解しているか
- 障害を受容しているか
- 特性に対し、対処法を持っているか
自分の得意不得意を理解しているか、自分の特性を理解し、受け入れているか。受け入れたうえで、不得意に対してどう対処しているか、を見ています。
では、面接での配慮事項に対するやり取りの事例をご紹介します。
面接でのやり取り事例

複数タスクが苦手という特性があります。配慮事項としては、業務はシングルタスクで支持を出していただきたいです。前職では複数のタスクを並行して行っていたため、頭が混乱し、ミスが出てしまったり、業務を行うのをすっかり忘れてしまうことがありました。

複数タスクが苦手、という特性があるのですね。ではその特性に対しての対策を教えてください。

複数タスクになる場合は、タスクを書き出し、優先順位をつけてからひとつひとつ業務に取り組むようにしています。配慮事項としては、自分が付けた優先順位が正しいか確認してもらいたいです。シングルタスクであれば、ミスもなく、集中力を保ちながら業務を行うことができます。
こういう “特性 + 自分なりの対処 + 相手にお願いすること” の流れが、人事には「自己理解がある」「成果を出したい」という印象を与えます。
あなたに合う支援を活用してスタートをスムーズに
「特性や配慮事項は分かるけど、実際にどう準備すればいいか分からない…」「自分にあった仕事を紹介してほしい」そんなときは、就労移行支援事業所や障がい者雇用エージェントを活用するのがおすすめです。専門の支援者があなたの特性を一緒に整理して、配慮事項のまとめ方をアドバイスしてくれます。
以下、私がおすすめするところをいくつか紹介します。まずは気軽に登録・相談してみてください。
キャリア相談
キャリア相談にものっています。お気軽にお問合せください。
まとめ
特性に対して、自分でどう対処しているか。自分では対処できないことが配慮事項になります。配慮してもらって当たり前、ではありません。
人事担当者は、自分の特性を理解し、それに対してどう対処しているか。配慮してもらうことで、どう成果を出すことができるか、を見ています。
ぜひご参考にしてください!


